最近、テレビとかでも目にする機会が増えた「ブロックチェーン」
なんとなく、ビットコインとかの仮想通貨に使われている重要な技
現在、ブロックチェーンは大きく分けて「パブリック型」「コンソ
今回はビットコインで使われている「パブリック型ブロックチェー
ブロックチェーンとは
ものすごく簡単に言うと「ビットコインの取引記録を皆でシェアし
もう少し詳しく言うと、ビットコインの取引データ等をまとめてブ
図を書くとこんな感じです。
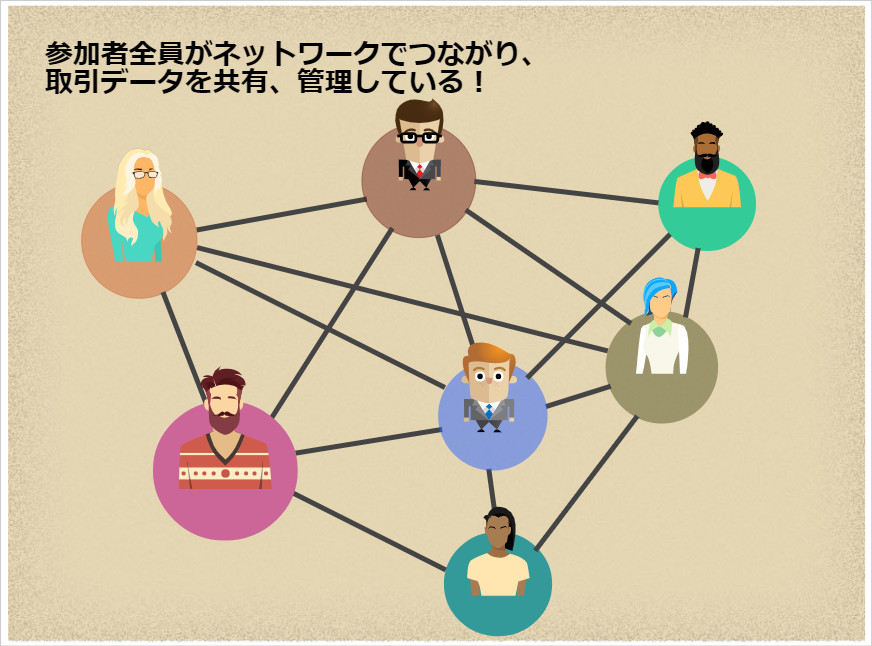
ビットコインは10分ごとに取引情報をまとめ、ブロックを生成して
ハッシュ値について
ハッシュ値は、ブロックの中に入っている「取引情報」、「前のブロック
ハッシュ値の特徴として、「ハッシュ値を元の情報に戻せない」と
この特徴がデータの改ざんを防ぐ役割を担
この特徴がデータの改ざんを防ぐ役割を担
nonce(ナンス)について
nonceは”number used once” (使い捨て)の略で、任意で作られた適当な数値です。
このnonceの役割は「ハッシュ値の文字列調整」です。
ブロックに使われるハッシュ値には「先頭から15桁の数字が0な
新しいブロックを作成する時には、このnonceの数字を変えて
この作業をマイニング(発掘)と言います。
この作業をマイニング(発掘)と言います。
マイニング(発掘)について
マイニングは簡単に言うと「頑張ってハッシュ値を見つけて承認作
先ほど触れたように、多数のマイナー(発掘者)が特定のハッシュ
ハッシュ値を見つけた後は、本当にそのハッシュ値が正しいかどう
51%のマイナーが正しいと判
51%のマイナーが正しいと判
まとめ
正直、複雑すぎて分かりやすく書けませんでしたw
頑張ったんですけどね・・・。
頑張ったんですけどね・・・。
そして思ったのが、技術的な内容の記事は書くのに時間がかかる!
完全に自己満の世界ですが、今後も勉強記事を書いていきたいと思
完全に自己満の世界ですが、今後も勉強記事を書いていきたいと思





